目次はこちらから
はじめに(2024.1.25更新)
本記事は私の肌で感じた主観と外部サイトによるデータを交えながらその年で起こったオンラインゲーム史を綴っていくページになります。
2017年以前は自身の記憶とデータのみになります。
本記事ではPC,スマートフォン,コンシューマー機を含めた様々なオンラインゲームの歴史と共にあなたも
1人のオンラインゲーマーとして”ゲーム”の行く末について考えて見ましょう。
オンラインゲーム20年を振り返る
オンラインゲームの歴史のはじまり
オンラインゲームの歴史とは、すなわちインターネットの歴史と同義でもあります。
インターネットの起源は1960年代まで遡りますが世界に初めて映像出力としてのオンラインゲームが誕生したのは1992年にNeverwinter Nightsというゲームです。
※映像を伴わないのであればCGIやPHPでのブラウザゲームは存在していました。
その後もDIABLO(1997年),ウルティマオンライン(1997年9月2日),EverQuest(1999年3月16日)などゲーマーの皆さんなら知らぬであろうビッグタイトルが2000年以前にリリースされています。
このタイトルのほとんどが記事執筆現在でも現役や、タイトルのナンバリングを変えて現存しているというのですから、驚きしかありませんよね。
それでは、2000年移行のオンラインゲームがどうなっていったかを覗いていきましょう。
2000年~2004年の日本はオンラインゲーム黎明期
(2017.9.28加筆)
この時点でオンラインゲームがはじまってから10年を経ているのですが私がゲームを始めたのがこの時期でした。
2004年は最盛期(黄金期の終わりくらい)だというご意見を頂きましたが、個人的にはまだまだ2004年は黎明期にあったと感じています。
最盛期を人口の面で考えれば上記にも記述しましたがこの2004年はオンラインゲームのサービス内容、ネット環境、PCスペックが加速的に変化していく年でした。
2000年から2004年にサービスを開始したゲームの一例を紹介します。
この時代はちょうどWindows2000及びMEからWindowsXPへの切り替えの時代でもあり、日本の一般家庭のインターネット回線にブロードバンドが普及しはじめた時代でもあります。
今では当たり前になった高速回線である光回線もこの時期にサービス開始をしましたがカバーエリア普及の問題もあり、ADSLが未だ主流の時代でした。
ISDNからADSLになったことによって安定した回線速度を得ることができ、オンラインゲームはより短時間に多くの通信が行えるようになり高品質になっていきます。
日本でも名だたる有名タイトルがサービスを開始したのもこの時期でファイナルファンタジーはコンシューマゲームIPとして早い段階でオンラインゲームとしてサービスを開始していました。
| 開始年 | ジャンル | タイトル |
|---|---|---|
| 2001年10月 | アクション | ポトリス |
| 2002年2月 | RPG | リネージュ |
| 2002年5月 | RPG | ファイナルファンタジー XI |
| 2002年12月 | RPG | ラグナロクオンライン |
| 2003年12月 | RPG | メイプルストーリー |
ただ、当時はグラフィックボードなどは一般のPCには必要なく家庭ごく普通にあるPCがゲームの要求スペックを満たさないことも多く、まだまだコンシューマ機でのゲームプレイ人口のほうが圧倒的に多かった印象です。今ではオンラインゲームをするのであれば当たり前のようにグラフィックボード(ビデオカード)のことを考えますが、当時はオンボードグラフィックでのプレイヤーが大多数でした。
2005年以降サービスの主流は定額課金から無料課金制に移行
オンラインゲームのビジネスモデルは基本的に月額〇〇〇円と言った定額サービスが主流でした。
2005年移行のオンラインゲームタイトルはPCとインターネット回線の爆発的な普及と月額課金プレイから従量課金プレイに課金形態が移行したことにより誰でも無料で始めることができることで、ゲーマー人口とサービス開始数も増えていきました。
人気に拍車がかかったのが2Dゲームで、やはりまだ3Dゲームは上述した通り要求スペックがまだ高く2Dゲームのほうが人口は多かった気がします。
ちなみにこの年に生まれた代表的なゲームに「RED STONE」や「大航海時代ONLINE」、「マビノギ」等がありました。
このあと、CPUやグラフィックボード(GPU)の性能が指関数的に上がっていくことで高品質なゲームが続々と登場していきます。
2007年 市場規模の拡大が及ぼした功罪
オンラインゲームが順調に市場規模を拡大するにつれ問題が顕在化してきたのが”BOT“や”チートツール”
これは自動操作やゲーム内の変数を意図的に変更するなど、ゲーム運営の意図しない方法でゲームプレイをすることです。
なぜこのようなことをするのかは明白で、ゲーム内のアイテム、通貨を実際の法定通貨(円)に変えることができるようになったからです。
“できるようになった”という言い方は正確に言うと間違いで、「現実のお金を払ってまでも、ゲーム内アイテムや通貨を欲しがる人が増えた」結果、ゲーム内のアイテムという電子データに価値が生まれたからなのです。
これは、プレイヤーだけの問題ではなく、運営側の問題でもあります。
月額課金のビジネスモデルから従量課金の方が儲かる理由は皆さんご存知の通り”ガチャ”の存在が大きく影響していて、希少なアイテムや付加価値をつけることによってそれを手に入れるために課金させるのが主流となっていたオンラインゲームのシステムが原因であり、わざわざ確率に任せて手に入れられるかわからないアイテムのために課金する人よりも、少々値が張っても確実に現実の通貨で取引したい人が増えていったのです。※これがRMT(リアルマネートレードと呼ばれます。)
ほぼすべてのオンラインゲームではこのRMTは※1規約により禁止されていましたが、システムでトレードを排除できない以上歯止めが効かなかった結果、韓国や中国で、日本のゲームを自動操作等でプレイし、得たアイテム通貨を現金にする行為が横行していきました。
オンラインゲームの市場と同時にRMT市場も拡大をはじめ、多くの取引サイトが生まれました(ほとんどが国外サイトでした)
※1…現在はゲーム内マネーを公式に現実通貨と交換できるゲームも存在します。
BOTはゲームにどう影響を与えたか
BOTが存在することによって起こりえる不利益は以下になります。
- ゲーム内アイテムの価値が上がる(通貨を大量に生産するため)
- ゲームサーバーに余計な負荷がかかる
- 運営元に入る資金が間接的にRMTに流れる
- 円の国外流出(価値が高い円を売って自国通貨にする)
ターゲットにされるのは流動性と貨幣価値が高い人気のあるゲームの通貨で、通貨は基本的に戦闘をすることで誰でも手に入るので、自動操作で戦闘をするBOTが増えるとゲーム内の通貨の供給が過多になりゲーム内通貨の価値がどんどん下がっていきました。
その結果どうなるかというと、ゲーム内アイテムの価値が上昇し、ますますアイテムを現金で買うという負のスパイラルが作られていきます。
BOTやチートツールの存在はここからしばらくオンラインゲーマーと運営会社につきまとうことになります。
このころからオンラインRPGは少しずつ”時間をかけてレベルを上げ強くなる“から”お金をかけるとその分強くなる(Pay to Win)“にゲーム性がシフトしていきます。
2008年 対人特化型オンラインゲーム(FPS)が増える(流行る)
オンラインRPG人口の増加と、市場規模の拡大に成功した日本のオンラインゲーム業界はパソコンパーツのコストや性能の上昇に更に後押しされ拡大していきました。
日本で流行する数年前から海外ではBF(バトルフィールド)やCS(カウンターストライク)が盛り上がりを見せ始め、日本でもこの時期にサービスを開始したゲームタイトルにオンラインFPSゲームが増えていきました。
今までのMMORPGはレベルが全てでお金をかければ強くなれるのに対し、始めたばかりでも実力さえあればゲーム時間や課金額に関係なく対等にプレイヤー同士が対等に勝負できるとFPSは課金額に比例して強くなる環境が増え始めていたMMORPGにはない魅力で、RPGに疲れたオンラインゲーマーにも支持されました。
※FPS・・・First-person shooterの略 1人称視点で行われるシューティングゲームのこと
ゲーム内コミュニケーションにも変化が
FPSが与えた影響はゲーム性だけに及ばずこの頃からゲーム内でのコミュニケーションツールとしてVC(ボイスチャット)が
導入され始めました。今のVCと言えば皆さんはSkypeやLINE電話,Discord等を思い浮かべるかもしれませんね。
当時はSkypeとゲームソフトの同時起動はPCに大きな負荷がかかったので現在のP2P型のVCではなくサーバー型のVCが軽くて人気でした。
2009年 対人ゲーム&ブラウザゲーム最盛期
2008年にIntelが発表したCorei7は仮想コアを用いた技術(HT)でソフトの多重処理が格段に楽になりました。
(ゲームに関しては当時はまだシングルコアでの処理しか出来ないソフトがほとんどでしたが。)
またFPSゲームの勢いは衰えず(Pay to win)要素が少ないFPSは、判断力や瞬発力などの人間のフィジカルな面にも大きく勝敗を左右することもあり、スポーツのように自分を使う道具(PCパーツ)など周辺機器に拘るユーザーが現れはじめました。
PCスペックによるゲームの快適さがプレイヤーの戦績に大きく影響を及ぼすことになりますので3DのFPSゲームを快適にプレイしようと多くの方がグラフィックボード(ビデオカード)を搭載し、マウスやマウスパッドにも拘るユーザーをターゲットにしたPCパーツメーカーが専用ブランドを発表したりしました。
3Dゲームへの移行が本格的になっていた2009年ですが時代と逆行したように2Dゲームが流行りました。
「アメーバピグ」です。以前はCGIなどを用いていましたがFlash主体で動くようになったブラウザゲームは自由度が上がってもプラットフォームはウェブブラウザなので要求スペックが低く、クライアントソフトのダウンロードやインストールもいらないということで低年齢層や女性層に大きな支持を受けました。
当時ブラウザゲームの二大巨頭はソーシャルネットワーク事業を主体とするmixiとアメーバピグを運営する『サイバーエージェント』でした。
ブラウザゲームはここから成長を見せるのですがプラットフォームであるFlash自体の脆弱性とHTML5への移行問題である大ヒットゲームが出てくるまではしばらく停滞していくこととなります。
面白いことにこのmixiとサイバーエージェントはこのあと別の形で成長することになり、ブラウザゲーム事業は別の巨大会社が名を馳せることになります…
また、低年齢層のコミュニケーション主体のゲームであるがゆえのリアルな対人問題等(出会い系サイトのような使い方で起こるストカーカーや人間関係の問題)もありました。
そしてハードウェアの世界では、ガラケーがスマートフォンに姿を変え始めたのもこのころでした。
※ちなみにアメーバピグは約10年後の2019年12月2日22時に惜しまれながらもサービスを終了しました。
2010年&2011年 ガラケーとスマホで揺れるモバイルゲーム市場
この年はPCオンラインゲーム業界ではMOゲームが賑わいを見せます。
オープンワールドのような広大なMAP等はありませんが制御しやすくMMOよりも自由度が高いアクションゲームに最適ということでドラゴンネストやMHF(モンスターハンターフロンティア)などが人気になっていきました。
またモバゲーやグリーといった携帯ゲームのゲーム会社がガラケーアプリをプラットフォームとしてSNSゲームをリリースしてから数年、
携帯ゲーム人気の一時代を築きました。
後にモバゲーは社名をDeNAに変更。野球チームを持つまでに成長していきます。
探検ドリランドや怪盗ロワイヤルなどヒット作を生み出しますが、モバイルゲームの時代の流れは確実にスマートフォンへと移行していきました。
ちなみにAppleからiPhone4が発売されたのも2010年でした。
2012年 あの”怪物”ゲームが市場を席巻&PCゲームタイトル開始数最多でオンラインゲーム市場は最盛期に
この年スマートフォン市場が爆発的な成長を見せiphone4を筆頭にスマートフォン所持率が飛躍的に上昇した年になりました。
同時にオンラインゲームサービス開始数が一番多かった年でもあります。
実態はアプリによるゲームが大半ですのでPCオンラインゲームは新たなムーブメントは生まれず、似たり寄ったりなゲームがスマートフォン、PC共に溢れる市場となっていきます。
そんな中アプリゲーム業界ではガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社が販売したゲームアプリ”パズル&ドラゴンズ“がiPhoneとアンドロイドのアプリゲームのダウンロードランキング1位となり市場を席巻。
1ヶ月の売上が数億円になるなど爆発的な人気とその画期的な課金システムにならい、様々な会社がスマホゲーム市場に参入しアプリゲームは戦国時代へと突入する時代のきっかけになりました。
「パズドラ」の作り出した曜日や緊急クエストや課金ガチャのシステムなどは今やアプリゲームのロールモデルとなり、現在もパズドラ共々存在し続けています。
2013年 スマートフォンゲーム戦国時代に「SNSの申し子が吼える」
スマートフォン(高機能携帯電話)の登場は人々のコミュニケーションの在り方を変え今まで電話やメールでのやりとりがLINEになったり、友人への近況報告がFaceBookに、そして愚痴の掃き溜めがTwitterになるように人々の情報発信ツールも多様化していきます。
そんな中ひとつのSNSの灯火が消えかかっていました。
そう・・・その名もmixi
mixiは従来特定の隔離されたコミュニティにより同じ共通点を持つ仲間と深いコミュニケーションを行うことができるSNSでした。
しかし、入会は18歳以上で招待制だったことや、世の中のスマートフォンの普及率が上昇したことによる他のSNSの台頭によりオープンで気軽な繋がりを求めてmixiを離れていきました。
(※のちに入会制限がなくなりmixiページもGoogleにindexされるようになりました。)
スマホ主体のSNSアプリにユーザーを奪われた苦しい状況の中でmixiを救ったのは皮肉にもスマホでした。
RPGとフリック型アクションを融合させたアクションRPGの『モンスターストライク』は5000万ダウンロードを超え赤字転落したmixiをV字回復させました。
その後もDLの勢いは衰えずAppStore&AndroidStoreでトップセールスにランクインし続けています。
2014年 サービス開始数とサービス終了数がほど同一に
iPhone4が発売されわずか2年で血で血を洗う戦国時代に突入したスマホゲーム市場はモンストとパズドラの2強が君臨し続けアプリは現れては消えていきました。
とうとう新規サービス開始ゲームとサービス終了ゲーム数がほぼ同一になり数撃てばあたるだろうの考えでゲームを送り出してはサービス終了を繰り返す運営会社にユーザーのゲームに対する信頼は下がっていく一方でした。
その中でも、スマートフォンゲームではSygamesが開発しモバゲーが運営する「グランブルーファンタジー」やコロプラが「白猫プロジェクト」を開始し、多くのユーザーを獲得して現在に至っています。
一方ブラウザゲームでも2013年に角川が制作しDMMが配信した”艦これ~艦隊これくしょん~”がヒットし、第2の艦これを狙え!と女の子と全く異なるジャンルを組み合わせたゲームがどんどん作られていきます。
2015年 スマホゲームの成熟と巨大版権の兆し
ほとんどの人がスマートフォンを手に取り、ゲームをするようになった2015年
サービス開始をしたゲームとサービス終了したゲームの比率はそのままに全体のゲーム数が減少していきます。
いわゆる寡占化です。
パズドラ&モンストはアプリダウンロードランキングに居座り続け、スマホゲームの成長はあまり見られなかった年になりました。
しかし、メガヒットを放ったタイトルが王者パズドラとモンストを襲いました。
Fate/Grand Orderです。
Fateシリーズのオリジナル作品で多くのファンに愛されているタイトルです。
歴史上の偉人と壮大な物語はユーザーを魅了し、RPGアプリのトップに躍り出ます。
このあと数年、パズドラ、モンスト、FGO(FateGrandOrder)はセールスランキング御三家と呼ばれるようになります。
一方そのころ、PCのMMORPGでは「黒い砂漠」というゲームが人気になり、その自由度の高さと高いグラフィックでPCゲームでは久しぶりのヒットとなりました。
ゲーマー御用達のコミュニケーションソフト「Discord」がリリースされる
ボイスチャットがコミュニケーションの主流になり、FPSに限らずRPG等でも当たり前に通話するようになりましたがこのディスコード以前はSkypeやTeamSpeakが主流のツールでした。
そこへ現れたDiscordは両ソフトの良いところを併せ持ち低遅延でクオリティの高い通話を無料で提供することでゲーマーを中心に爆発的な普及をもたらしました。
2016年 ついにあの”モンスタータイトル”がモバイルに進出
20年にわたる長い人気もさることながら全世界に圧倒的なファンを持つ「ポケットモンスター(以下ポケモン)」がAR(拡張現実)の機能を引っさげてスマホアプリ市場にやってきました。
その影響は世界的で下記のギネス記録を樹立しました。
- モバイルゲームの中では最初の1カ月で最も売り上げを集めた。
- モバイルゲームの中では最初の1カ月で最もダウンロードされた。
- 世界のモバイルゲームダウンロードチャートの中では最初の1カ月で最も多く同時にトップを獲得。
- 世界のモバイルゲーム売上チャートの中では最初の1カ月で最も多く同時にトップを獲得。
- モバイルゲームの中では売上高1億ドルに最も早く到達した。
※wikipediaより引用
老若男女問わず現実世界とポケモンを融合することで、ゲーマーの外出が増えたり、ポケストップ機能を集客に利用できたりとARやGPSといったスマホの機能をフルに使用したこのゲームは外を歩けばプレイヤーがすぐに見つけられるほどに人気になりました。
と、同時に大きな社会問題となったのが「プレイをしながらの自動車運転事故」です。
ポケモンGOに搭載されているGPSでの距離測定機能は元々徒歩でのプレイを目的として作られていたので運転手がプレイしながら運転することによって引き起こされた事故が多く発生し、対策を講じることになりました。
2017年 PCゲームの新たな面白さを魅せた”バトルロワイヤルゲーム”
2017年は数年ぶりにPCゲームに大きなムーブメントが起こりました。
100人同時プレイバトルロワイヤルゲーム「PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(以下PUBG)」全世界で5000万本、プレイヤーは4億人以上という未曽有の大ヒットを遂げました。
TPSバトルロワイヤルゲームは全く新しいジャンルのゲームで、高精細なグラフィックを採用したPUBGは一般的なPCではプレイできず久しぶりにゲームにPCスペックが追い付かないという状態になりました。(アーリアクセスということもありソフト側の処理も問題ではありましたが)
また、Dead by Daylight(デッドバイデイライト)も発売こそ2016年ですが2017年はSteamでの販売も好調で、翌年2018年ではPS4で日本版が配信されると認知度が一気に上昇し、人気ゲームとなりました。
多くのゲーマーがグラフィックボードの新調したのと同時に仮想通貨が大流行し、マイニングにグラフィックボードを使用するため大量の買い占めが起こりグラフィックボード市場は稀に見る高騰が起こりました。
このゲームの人気にあやかって同じようなゲームシステムをもつタイトルがスマホでリリースされますが、そのゲームが本家を超えた大ヒットすることでPUBGとの訴訟問題に発展していくこととなります。
日本でも対戦ゲームが身近な存在となり、「eスポーツ」は2017年に命名される。
今ではゲーマーに馴染み深い「eスポーツ」ですが、フロリダで開かれた2017 American Copy Editors Society conventionにて、AP通信が「esports」で統一することを発表しています。
それまでも格闘ゲームを中心に海外ではゲームカテゴリで盛り上がりを見せる分野でしたが、昨今のFPSブームを受けてゲーム全般をスポーツ競技として発展させていく声が多く寄せられました。いろいろな呼び方がありましたがこの頃からはeスポーツで統一されていくこととなります。
しかしながら、日本では法規制やライセンス等の様々な問題で大きなムーブメントを起こすには一筋縄ではいかない状況が続いていくことになります。
任天堂がコロプラと訴訟問題に
ライセンスといえば、ゲームの操作システムを巡って任天堂がコロプラに訴訟の提起を行ったのがこの年12月になります。界隈では有名な「ぷにコン」というキャラクター操作のインターフェースです。
本件に関わる分かりやすい記事はこちらのLegalSearch様がわかりやすく訴訟までの経緯を説明してくれています。
ゲームジャンルのトレンドは2018年を期に各社の発売ゲームジャンルが似通ってきており今では大人気ゲームに名を連ねるあのタイトルが法廷で争うことになっていきます。
2018年 ゲームシステムの権利ってどこにある?同じようなゲームが溢れる
2018年発売のオンラインゲームで最も優秀な作品と言えば間違いなくコレでしょう。
そうです。モンスターハンターワールドです。(以下MHW)
約10年振りにSonyに帰ってきたMHWはPC(Steam販売),PS4で累計1200万本を超える売り上げをたたき出した紛れもない“モンスター”タイトルです。
伝統的な4人協力プレイもさることながら歴代モンハンでプレイヤーが不満に感じていた点を細かく改善しており、任天堂ハードにはできない高画質なグラフィックでPS4の売り上げにも大きく貢献しました。翌年2019年には続編となるIB(アイスボーン)がDLCとして登場しました。
さてPCゲームはどうだったかというと、前年に人気になったPUBGやDBD(デッドバイデイライト)がスマートフォン向けに改良されてリリースされています。
PUBGのバトルロワイヤル形式のシステムは荒野行動や、フォートナイトなどが類似のシステムで大きくユーザーを取り込んだ結果、会社同士の訴訟問題にまで発展する結果となりました。

類似システムで別の会社からゲームが出るなんてことは別に珍しいことでもないのですが2018年に関してはそれが顕著に現れた年でした。
2019年 ゲームの新しいカタチとスマホ市場に再びモンスターが襲来
2019年3月19日,Googleは,独自のクラウドゲームプラットフォームを作成。
それは「Stadia」(ステイディア)と呼ばれ2019年中に北米および欧州市場でサービス開始すると発表しました。
今や全世界で関わっていない人がいないほどの影響力をもつ大企業がついにゲーム業界へ参入をしました。
Googleが提供するStadiaの最大の特徴は『クラウドゲーミングサービス』であること。
クラウドゲームとは、コンピュータゲームをストリーミング配信するサービス。クラウドコンピューティングという用語が普及する以前はゲームオンデマンドと呼ばれていた。ゲーム以外のアプリケーションを同様な技術で稼働させる事をシンクライアントと呼ぶ。引用: wikipedia
このサービス自体は新しいものではなく、数年前から小さな規模ではありますがサービスが提供されていました。このクラウドゲーミングサービスによって、多くの利便性をユーザーが受けることが可能になります。
既にビデオカードを販売するNVIDIAやAMDも同サービスに参入しており、MicrosoftとSONYはAzureでの配信ストリーミングサービスで手を組むことが発表され、クラウドゲーミングサービスを舞台に企業通しの戦いがすでに始まっています。
そして、2019年9月に新たなモンスタータイトルがスマホゲーム市場に現れました。
そうです、ドラゴンクエストウォーク(以下DQW)です。
ゲームの基盤となるのはGPSを利用したいわゆるポケモンGO型の位置情報ゲームで現実世界の出歩く先々でモンスターと戦闘を行い、ダンジョンを制覇するというRPGには鉄板の仕様となっています。世界に幅広いファンを持つポケモンGOとは対象的に、ドラゴンクエストは国内で圧倒的な人気を誇ります。
元々RPGゲームであったドラクエとの相性は言うことが無く抜群でセルラン(セールスランキング)トップに躍り出ます。個人的には、ポケモンGOほどのインパクトはなかったものの課金要素が強くリリースから一ヵ月後の売り上げは93億円とのことです。(ちなみにポケモンGOは128憶円相当)
日本のアプリゲーム市場はアプリが溢れかえり、近年システムのイノベーションが起こらないのでユーザーは闇雲に新規ゲームをダウンロードすることはしなくなり、知名度の高さが初動ダウンロード数に直結する時代へと進んでいきます。
もう一つのモンスタータイトルといえば「Apex Legends™(エーペックスレジェンズ)」が日本で爆発的に人気になりました。
元々コンシューマー用FPSゲームである「タイタンフォール」を題材としたスピンオフタイトルでサービスを開始したAPEXですが、PUBG,フォートナイト,荒野行動とは違ったカジュアルなグラフィックやスキルシステム、キャラクター選択方式など今までにあったバトロワ系FPSとは違った面白さがププレイヤーに新しいゲーム体験を与え、シーズンを重ねるごとに細かい修正や改善を重ねることでアジア圏で瞬く間にプレイヤー数を獲得していきました。
爆発的に増えるユーザーと共に、チートツールやコンバーターなどのプレイヤーの技量をアシストする外部ツールが蔓延し、数年に渡って問題になっていきます。
2020年 歴史的なパンデミックとゲームの力
2019年12月に中国の武漢市で発生したと思われる”新型コロナウイルス”の猛威は世界中の人々を恐怖に陥れ、人と人との交流を完全に遮断することとなりました。世界中の人々が外出せず”自宅で休日を過ごす”ことになってゲームは子供たちだけでなく大人の心の拠り所になりました。
NintendoSwitchが品切れ
自宅で自粛を行う人々が余暇を楽しむためにNintendoSwitchを欲しがった結果品切れとなり、フリマアプリ等では定価40,000円ほどのNintendoSwitchが60,000円前後での転売も確認された。人気ソフト「あつまれどうぶつの森」が2019年から2020年に延期された影響もあり、中国では同ソフトを使用した政権批判もあり流通が停止する事態にも及んだ。
>【悲報】あつまれどうぶつの森 ゲーム中で習近平の葬式ごっこや中国政府の批判をした為中国で販売停止になる [703385583]https://t.co/DwUFz2pRnM pic.twitter.com/Gx2UEbqRKV
— 菜 (@torta_fi) 2020年4月10日
2021年 世界的半導体不足の中ファン待望の覇権アプリがついに出走
コロナウイルスが流行から新年を迎え、経済が立ち直り始めたころ、世界的な半導体不足の問題が発生しました。車の生産や5Gなど半導体の利用先は多岐にわたります。2021年初頭からパソコンパーツであるビデオカード(グラフィックボード)も品切れが相次ぎ、価格高騰が発生しています。
そんな中、2021年2月24日にスマホアプリ業界に新たな覇権アプリが誕生しました。
ウマ娘 プリティーダービーです。
リリースから月間100億円オーバーを叩き出すまさしく暴れ馬なアプリですが、なんと開発が発表されたのが2016年で当初のリリースは2018年冬でした。その後クオリティ向上を目指しリリースが延期となり、開発期間が5年にも及びます。
2022年 シューター系ゲームのユーザー争奪戦は苛烈を極める
まずは数年前から発売している人気のPS5は未だ抽選販売で希望するユーザー全てに行きわたっていません。そんな中初期製造ロットの販売が終了し、PS5はマイナーチェンジを施されます。既に手に入らない憤りからPS5の購入を諦め、PCにゲームのプラットフォームを移し始めるユーザーが多数いました。
PCといえば、スペックに頼らずインターネット回線があれば快適にゲームが出来ることでスタートしたGoogleのStadiaでしたが、2022年9月30日にサービス終了を宣言しました。困ったのは同プラットフォームで新作ゲームをリリース予定であったゲーム会社です。事前に効かされていなかったらしく、開発者もGoogleの対応に憤りを感じていたようです。
2017年にリリースされた”PUBG“から始まり、コロナ禍でユーザーが爆発的に増加した”バトルロワイヤルゲーム”ですが2022年はタクティカルシューター系ゲームがTwitchの視聴者数やTwitterトレンドで勢いを確認できるようになりました。また、コロナが終息の兆しを見せる中で人気配信者や
ValorantやOverWatch2、GUNDAM EVOLUTION TPSではSplatoon3など一人勝ちしていたAPEXが3年目を迎え、ゲームに新しさが見出せず新たな刺激を求めユーザーが移動しているようでした。有名配信者やeスポーツによる大会等シューター系ゲーム自体の人気は衰えずこれから出てくる新作ゲームではさらなるユーザーの奪い合いが予想されます。
ちなみにこの年11月には育成RPGゲームの金字塔、ポケットモンスターシリーズの最新作「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」が発売。世界で2000万本以上を売り上げシリーズ歴代4位の売り上げとなっています。
2023年 各社ゲームハードは成熟期へ 名作の新作が続々リリース
コロナの流行が落ち着き、ほとんど日常に戻った2023年。
この年は往年の名作シリーズが発売され大いにユーザーを沸かせました。
最も売れたソフトがこちらの3タイトル
| ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム |
| ピクミン4 |
| スーパーマリオブラザーズ ワンダー |
どれも任天堂の誇る名シリーズですね。playstationからはファイナルファンタジーXVIが売り上げ上位に。
ハード発売から7年目を迎えるnintendoswitchが圧倒的ユーザー数を抱えている反面、SONYのPS5は発売年からの転売や製造難を解消できずソフトウェアの売り上げに影響が出ています。
そんな中新型PS5の発売がされたのも本年、現行機種を値下げすることで供給の安定が可能になりました。(やっと)
ハード自体は両社ともに発売から3年以上が経過し、ソフトのタイトル数は潤沢になりました。
アーマードコアが十数年ぶりの新作が発売されたり、ストリートファイター6はeスポーツ界を盛り上げました。
新しい技術やシステム等はこれといって革新的なものが生まれず、良くも悪くもゲーム全般が成熟した年になりました。
※この年のswitchダウンロードランキング1位を飾ったのはゼルダやマリオではなく
唐突に表れた果物落としゲーでした。
240円という低価格や、配信者がプレイしたところから火が付き翌年1月には600万ダウンロードを記録しました。
2024年 Working hard on writing…
※出典
Impress Watch 「年表で振り返るブロードバンドの歴史」
生存のための存在証明 「ネットゲームの歴史(1992-2009)」
MMO総合研究所「正式サービス年表」
wikipedia「エレクトロニック・スポーツ」





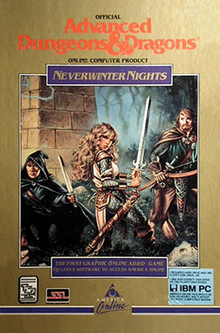

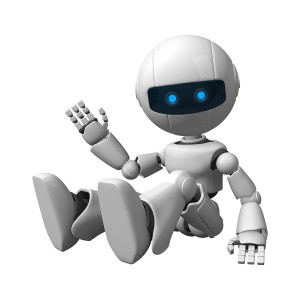














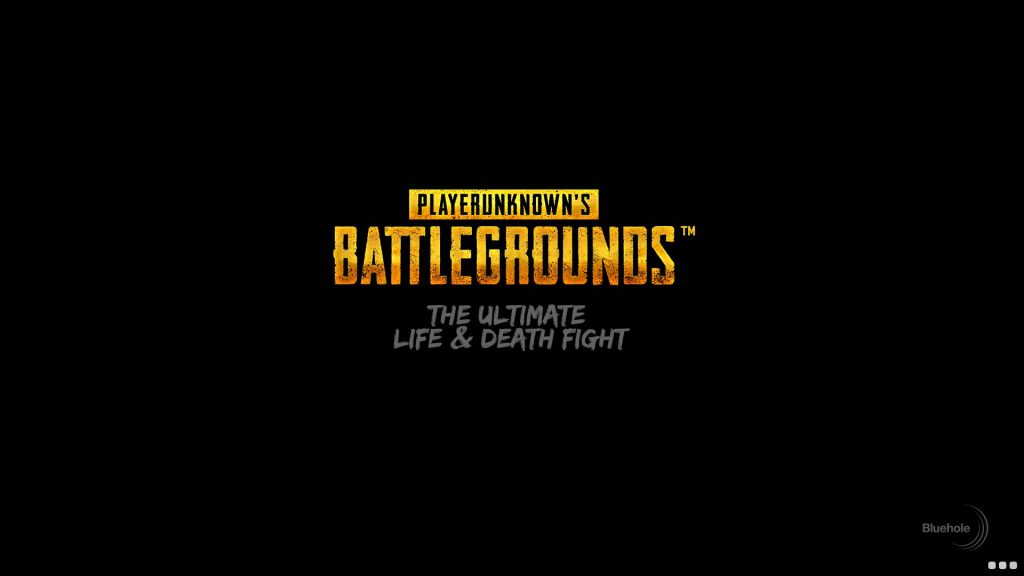


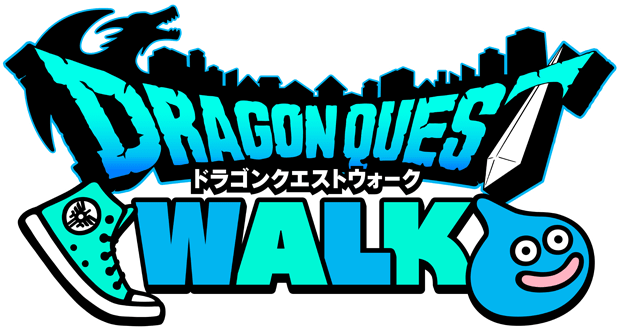










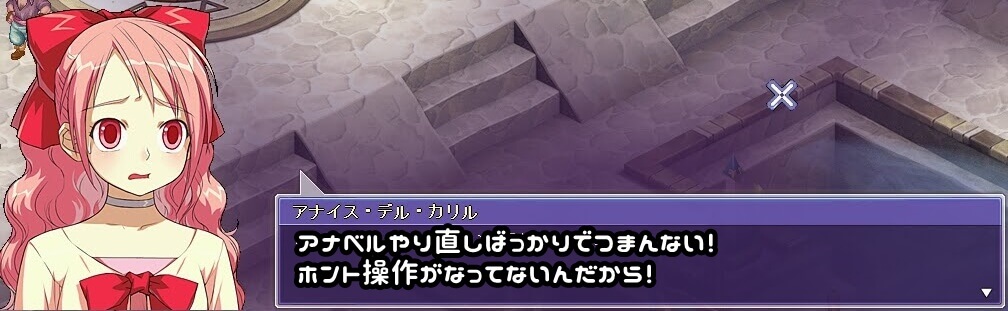
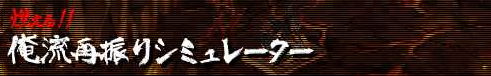
どうも、現在30前後当時小学生のネトゲおじさんです!、いや~人生早く終わりたいですね~やっとそれなりの経営が出来る様になってきましたけど熟練の40.50.60代の方々の手腕には日々驚いてばかりですわ! っとそんなことよりもネトゲですね。
自称ライターさんの残したこの記事はとても素晴らしいと思います!!
Neverwinter Nightsが1992年と言う出落ちから始まり自称ライターとしては抜けている事や主観的な決め付けを事実としている点も多々ございますが。素晴らしいと思います!!
それは…他にこれほどの長文で大体合っている歴史を書いてる記事が見当たらないからです。 まさに愛!! 愛(主観)によって生まれ主観(愛)によって書かれている!!素晴らしい! 読んだ人が賛否両論語り合いたくなる様なとても楽しめた記事でした。是非これからも記事を書いて下さい!応援してます!! PS.人間なんてみんな違う人生なんで~〇〇がいつ頃なんて正解の無い事、感じた人によって時期のずれが2.3年合っても当たり前でむしろ時期がずれていようがそういう事が感じられる時期がネトゲの歴史に合った事実が重要じゃね~(鼻ホジッ ってか方程式でもあるまいし答えなんて無いんだから主観で語る以外道ねぇよ!歴史なんて人が積み上げてきた主観なんだよ! 的なテキーラ
他コメさんの2004年がオンラインゲーム黄金期の末期という話は、まぁ、90年代のプレーヤーの人と一緒にプレイしてた自分(まるで頭を撫でる様に教えて頂いてた日々)でも気持ちはとても分かりますね。もちろん自称ライターさんみたいにその当時を知らない人からしたら人口とタイトル数、ネットワーク環境や今のネトゲ業界の現状などからの推測しか出来ませんので、2004年は最盛の年というよりは大きな転換の年となっていた印象しか無い気持ちもよく分かります、自分も90年代については耳にタコが出来るほど昔は良かったんじゃ~・・と、聞いた話が大半なので転換としか思わない自称ライターさんの気持ちも分かります!!ですが聞いた話が大半で実際に00年代からプレイしてる自分でも2004年代は黄金期の末期だと思う気持ちは十分理解出来ます!お二人とも正しい事を言ってます!お二人の言っている、定額制が減り始め無料になったりサービス終了したりと黄金期の末期を感じた気持ちも、その時代をデータによる推測しか出来ないので今に繋がる全ての歴史から客観的に判断しようとすると転換の年という印象しか無いと言う気持ちもとても分かります。
黄金期なんて人に寄って違いますので、俺なんて今日が明日が黄金期かと思います技術が!テクノロジーが!この進化していく時代の先が眩しくて仕方がないです。
ちなみにもう気が付いてらっしゃるかと思いますが、このサイトを楽しんでいる方の為にも書いときますと、このお二人の認識のズレは定額や無料などのサービスの制度や環境やタイトルやその数、ゲームや人口などデータ的な物などその全てが原因でありそれ以外にも原因があるんだと思います。その上で全くの別人が別々の体験をしているからずれているだけの当たり前の事です、 お二人とも自分が愛したネトゲでの経験の中から語るとても正しい事を言っていて事実両方正しい事です。素晴らしい!!
そして何よりこの二人の会話を完成させているのが。その後の他コメのシンヤさん
この二人の認識のズレの中に無い数字だけでは分からないプレイヤー層の違いの話を裏付けているッ!!
プレイヤー人口1と言う数字の1だけでは語れない事は当時の中学生と今の中学生を見ればよく分かります、他コメのシンヤさん【当時2004年当時は、中学生で自分用のPCとかもまだ持っていなくて、ネットカフェとかでメイプルストーリーやったりTWやったりしていました。(すぐやめましたが…)】の存在を考えて頂けるとよくわかると思います。
昔はオンラインゲームは大人やお金持ちの物でした。今は子供やニートなどが大半です。
2004年当時ですら一般的な小中学生は毎月2~3千円しかない貴重なおこずかいを使っても月に1回2回・・それも数時間だけしか出来ないんです。もちろんそんな貴重なおこずかいをそれに費やす様な子もほんのひと握りで少なく、それもネトゲ業界が定額制サービスからアイテム課金型サービスになってきたから出来た話ですメイプルストーリーやTWなど月額がいらないから出来たんです。。1990年代だとプレイするだけでも無料では無い定額制が大半なので毎月プレイしてなかろうがお金もかかりますしネットカフェの店舗数もかなり違い子供の力だけでは厳しい事がとても分かります。 そもそもそのメイプルストーリーですらcmが2005年に放送されて認識が広まり始めたのでオンラインゲームなんかしてたらうちの子はなんか変な事をしてる。。なんて感じで大人ですら今ほどの認識は無いので2004年なんてオンラインゲームの存在すら知らない子が大半です。
今時の小中学生はほとんどがオンラインゲームを出来る端末を持っていて時間があればいつでもok!!中には、コロナ騒ぎで学校が休みで一律給付金で買ってもらったpcを自室に置き奇声を上げながら友達と夜通し.エンジョイ!!ですからね!ゲームがオンラインなのは常識ですよ!アメリカの首都を聞けばNYと答え、オンラインゲームをしてると言う子にLANケーブルを渡すと充電器ですか?コレと答え。TV付けてればオンラインゲームのCMを見ない日は無いぐらいでhubやルーターをwifiと呼びオンラインゲームが出来る様にwifiの設定は親がやるのが当たり前、そんな感じの子が大半です。
もちろんこれは小中学生に限らずオンラインゲームをプレイしている割合で言えば全ての世代に当てはまる事です、プレイヤー達のリアルの正確な割合なんて誰もわかる訳がありません、ですが今と当時だとプレイヤー層が大きく違う事は 確定的に明らか ですね!
1997年からオンゲ語れとかどんだけ人生終わってるネトゲおじさんだよww
2004年ってオンラインゲーム黄金期の末期じゃん。
できるなら1997年前後から、最低でも2000年から語らないと歴史にならないよ。
コメントありがとうございます!
私がオンラインゲームを始めてからの歴史となっておりますのでオンラインゲームのすべてを補完できず申し訳ないです。
しかしながら、黄金期を人口とタイトル数等で考えますと2004年は最盛の年というよりは大きな転換の年となっていた印象です。
オンラインゲームに必要なネットワーク環境もADSL主体のネット環境からFTTH(光回線)に変わりつつあったのも2004年でした(実際の普及は2005年あたりから)
それと同時に定額制サービスからアイテム課金型サービスへと移行するゲームが増大し、現在オンラインゲームが開始された数が最も多かった年は2012年だそうです(2000タイトル以上)
個人的な主観ではございますがここらへんがPCオンラインゲームの黄金期だと考えています。
とても勉強になりました。
当時2004年当時は、中学生で自分用のPCとかもまだ持っていなくて、ネットカフェとかでメイプルストーリーやったりTWやったりしていました。(すぐやめましたが…)
最近になってメイプルストーリーはスマホ版が出て、他のプレイヤーに「PC版ってどうなってるの?」と聞くと「過疎ってるよwww」なんて返事が返ってくる。(本当かどうかは確かめてません)
どんな流れがあって、ユーザーが移動したのだろう?と疑問に思っていたので、とても参考になる記事でした。ありがとうございました。
コメントありがとうございます!!
2000年-2005年の間にブロードバンド環境が整備されたことでネットゲームは多くのプレイヤーを獲得することが出来たと思います。
また、教育部分でもこの頃オンラインPCが学校に導入され始めたのも影響しているかもしれません。
スマートフォンの登場と既存のユーザーの高年齢化によって携帯端末に大移動したのは間違いないと思っています…